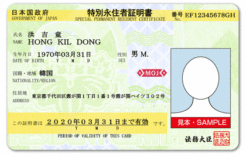一般永住者と特別永住者の違い
一般永住者と特別永住者の違い
日本に在留している外国人は日本政府から許可された「在留資格」を所持している。その中に「永住者」(一般永住者)と「特別永住者」という一見似たようなカテゴリーが存在する。
「在留外国人統計」(法務省)によると、2019年6月時点で永住者は78万3513人、特別永住者は31万7849人が日本に在留しており、両者をあわせると在留外国人総数(282万9416人)の約40パーセントとなる。
一般永住者とは「日本政府から永住資格を許可されて日本国に永住している外国人」を指し、申請して厳格な要件を満たしていれば許可が下りる。一般に永住者と聞いて思い浮かぶのはこちらだろう。外国人登録の「国籍・地域」別で見ると、中国籍、フィリピン籍、ブラジル籍、韓国籍が全体の約66パーセントを占めている。
一方で特別永住者の場合は、一般永住者のように誰でも申請できるものではなく、いわゆる在日旧植民地出身者が対象である。そのため、特別永住者の約99パーセントは韓国籍および朝鮮籍であり、その次に台湾籍(約0.3パーセント)が続いている。
1991年に特別永住者制度が誕生するまでの経緯は、旧植民地出身者が歩んできた歴史と密接不可分な関係にある。
日本国籍でありながら外国人として扱われた朝鮮人や台湾人
戦前、台湾編入(1895年)や韓国併合(1910年)によって朝鮮人や台湾人は日本国籍者として扱われるようになった。同じ「帝国臣民」ではあるが日本人と同様の権利が認められていたわけではなく、あくまでも国籍上だけの話である。
1945年8月に日本がポツダム宣言を受諾し、日本は敗戦。朝鮮や台湾の植民地支配は終わり、朝鮮人や台湾人は本国に帰還していったが、本国に生活基盤がない人は日本に残留することとなった。
在日旧植民地出身者は、終戦後も国籍上は「日本人」であった。だが、1947年の「外国人登録令」が台湾人や朝鮮人を「当分の間、外国人とみなす」と規定したことで、日本国籍でありながら外国人管理上は「外国人」として扱われるという不自然な状況が生まれたのである。
余談だが、この外国人登録令により「朝鮮籍」というカテゴリーが生まれた。これは外国人登録証(2012年以降は在留カード)に記載される出身地域を示すだけの外国人登録上の「記号」である。現在でも実際の国籍を表わしたり、証明したりするものではない。南北分断後には「韓国籍」というカテゴリーが誕生し、国籍上でも「大韓民国籍」が準備された。
だが、未承認国である国家の国籍は国内法では認められていないことから、「朝鮮民主主義人民共和国籍」(北朝鮮)だけはいまだに日本国内には存在しないことになっている。
サンフランシスコ平和条約で外国人となった旧植民地出身者
さて、外国人とみなされた旧植民地出身者にとって新たな局面となったのは、1952年4月28日に発効した「サンフランシスコ平和条約」である。
これにより日本は主権を回復し、正式に朝鮮の独立承認などが行われたが、条約の影響は在日旧植民地出身者にもおよぶこととなった。
日本政府は条約発効を機に、「法務府民事局長通達」(1952年)を出し、「条約発効にともない朝鮮人および台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する」とする見解を示したのだ。つまり、旧植民地出身者は突如として日本国籍を喪失することとなったのである。
このときの国籍喪失者を一般に「平和条約国籍離脱者」と呼ぶ。
一方的に国籍を剥奪したことへの非難は強いが、最高裁では「国際的承認を得たサンフランシスコ平和条約にともなうものである」として正当性があると解釈されている。
だが、条約そのものは国籍喪失について直接規定しているわけではないし、ドイツでは当時、オーストリアの分離にともなって国籍を選択させるという措置がとられたように、「国籍を選択可能にすべきであった」といった反論が寄せられる。
平和条約国籍離脱者=特別永住者
当時は、「日本国籍の喪失=日本の植民地支配からの解放」と捉えられていた面もあった。その一方で、外国人として国外追放や様々な制度上での排除が国籍を理由に可能となったわけで、旧植民地出身者がより不安定な立場に置かれることとなったのも事実だ。
とにかく、これ以降「元日本人」である平和条約国籍離脱者が日本国籍を再び希望する場合には、他の一般外国人と同様に「帰化申請」によって日本政府の可否判断を受けることが必要となったのである。
ちなみに、『日本統計年鑑』(総務省)などによると、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効当時は朝鮮籍者および韓国籍者が約56万人、台湾籍者約2万人が日本にいたと記録されている。冒頭で「特別永住者の99パーセントは朝鮮籍および韓国籍で、その次に台湾籍が続く」と紹介したが、当時の平和条約国籍離脱者の国籍割合がそのまま影響していると言える。
平和条約国籍離脱者のために用意された「法126」
さて、日本政府はサンフランシスコ平和条約発効により旧植民地出身者(平和条約国籍離脱者)を強制的に「外国人」にしたわけだが、従前からある在留資格のいずれかにその全員を即時に振り分けることは当然不可能であった。
だが、このままでは平和条約国籍離脱者の日本在留の法的根拠がなくなってしまうし、だからと言ってさすがに「不法滞在」扱いで国外追放するわけにもいかない。
これを日本政府は出入国管理令を改正して対応した。内容は、「別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」というものである。
この法律の名前は「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係所命令の措置に関する法律(昭和27年法律126号)」と長いので、この法律に基づく在留許可は「法126」または「126-2-6」と呼ばれ、その子どもについては「法126の子」と称される。
臨時的な法律であるが、その後も法整備がなされないまま年月が過ぎた。
1991年入管特例法制定により特別永住資格が誕生
1965年になって日韓の国交が正常化され、「日韓法的地位協定」が締結されたことで法126に変化が生じた。協定により「朝鮮半島出身者のうち1945年8月15日以前から引き続き日本に居住している韓国籍保持者」は協定発効5年以内に限り、申請すれば「協定永住」を取得することが認められたのである。
1981年には入管法が制定され、「日韓法的地位協定で協定永住を取得しなかった者でも、申請すれば無条件に永住を許可する」と改められた。こちらは「特例永住」と呼ばれる。
その後、大きな転機となったのは、1991年に制定された「入管特例法」である。これは同年、日韓両国の間で締結された「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」(日韓覚書)を受けて制定されたものである。
この入管特例法により、法126資格、法126の子資格、協定永住資格、特例永住資格とばらばらになっていた在留資格がようやく一本化され、「特別永住」というカテゴリーが誕生した。旧植民地出身者およびその子孫は、出身地(南北朝鮮、台湾)や世代(1世、2世など)を問わず、特別永住という在留資格に一括されたのである。
特別永住資格の「権利化」を求める声
1991年に特別永住制度ができて今日にいたるが、特別永住者らを中心に永住「資格」ではなく永住「権」を求める声があがっている。「特別永住者制度は権利ではなくあくまで資格であるため、日本政府の判断でこの資格をはく奪することが可能である」というのがその大きな理由である。
制度として見ると、一定の条件で資格は喪失する可能性がある。たとえば、特別永住者を含む在留外国人は出国前に再入国許可を受ける必要があるところ、手続きを踏まずに出国した場合はその時点で資格が喪失するものとされている。
かつて協定永住資格があったころ、ピアニストの崔善愛氏が資格を喪失したというケースがあった。彼女は外国人登録の更新時に指紋押捺(現在は廃止)を拒否したため再入国許可を受けることができず、そのまま出国したために協定永住資格を喪失したのである(崔善愛氏は外国人登録法改正により2000年に再び特別永住資格を獲得)。
これは協定永住の例だが、当然、特別永住者も再入国許可を受けずに出国すれば同様の事態となる。これに対しては、「再入国許可を受けて出国するなど制度に従えば資格ははく奪されることはない」という意見もある。それも確かに事実であるが、ここで重要なのは「権利ではなく資格であるために一定の条件の下ではく奪可能」という点だ。
「資格」である限り日本政府の判断で奪われかねないという不安
特別永住者制度の成り立ちについても手続き上の指摘がある。
前述した通り、協定永住資格は1965年の日韓法的地位協定に基づくものである。同協定は「条約」として国会承認を経て公布され、国内法としての効力を有するにいたった。一方、特別永住資格は1991年の日韓覚書を受けて法律を制定している。
両政府は「覚書」を条約同様に遵守する義務があるものの、日韓覚書については日本で国会の承認手続きがとられていない。
この手続き上の差異から、「条約に基づいて設けられた協定永住資格と、覚書に基づいて設けられた特別永住資格とでは重みが違う。将来的に日本政府が独断で特別永住者制度を改悪する可能性が残されている」と指摘されている。
植民地出身者とその子孫たちは、日本の植民地支配の結果として日本に住み続けているわけだが、日本人ではないことを理由に法律や制度に振り回され続けてきた歴史を持つ。
「資格である限り日本政府の判断で奪われかねない」という不安を持つのは当然と言えるし、「もし永住資格が権利化されれば、政府が法改正などでむやみにその権利を奪うことはできなくなる」という主張も理にかなっている。
旧植民地出身者たちが歩んできた歴史を考えれば、日本政府には特別永住者たちの「権利化」を求める声に真摯に耳を傾ける必要があると言えよう。
八島 有佑